どのような物にするか?)

| s設計編lo t1水冷編 |
|||
| 1.構想設計 | |||
|---|---|---|---|
| 何度まで冷やしたいか? 冷媒は何を使用するか? 冷やす方法は? 冷凍ユニット、冷凍ユニット+ペルチェ等 ベースとなる機器に何を使用するか? 冷風機、冷蔵庫、エアコン室外機、ウインドエアコン、冷凍機 |
|||
| 冷却可能温度と機器構成の関係 | |||
| 冷風機: | |||
| 冷風機に使用されるcompは、出力200W程度であり、 その吐出能力は0.7〜1m3/h程度と推定される。 compとしては高温仕様のため、高圧縮向きでなく、オイルも高温用のものが使用されていると考えられる。 単体で使用した場合、計算上、-60℃で50W程度の吸熱が可能。 ただし、この時のcompの圧縮比が17〜40付近であり、compの体積効率低下等により、-55〜-50℃辺り迄の温度が現実的。 ペルチェ3枚併用の場合、計算上では、eva-30℃、buffer-55℃で 40〜50Wの吸熱が可能である。 この場合も、圧縮比4〜10程度であり、冷風機として使用される時の 圧縮比2〜4に比較して大きく、eva-25℃、buffer-50℃付近が限界と 考えられ、ペルチェを使用するメリットは無い。 |
|||
| 冷蔵庫: | |||
| 冷蔵庫用compは、古い物はR12、最近のものはR134aを使用して おり、エアコン等のR22に比較して低温での能力は低い。 しかも、殆どがレシプロで高圧縮時の体積効率低下が激しい。 特にR134aは冷凍機用オイルも特殊ということも.... ただし、その用途が中低温用を前提としているので、そこそこの 結果は得られると思われるが、殆どその事例はない。 コンデンサ等の転用できる部品が少ないのも原因か..... |
|||
| ウィンドエアコン、エアコン室外機: | |||
| 電源容量や改造のし易さから、ウインドエアコン(*16*とか*18*)、 エアコン室外機6畳用(*22*)〜8畳用(*25*)の冷専機を使用したと すると、comp出力は500〜600W、吐出量2〜2.5m3程度と推定される。 compは、冷風機と同様に高温仕様。 単体で使用する場合には、冷風機より更に10℃程度低い温度迄は 冷却できると思われる。 ペルチェ3枚併用の場合には、eva-40℃、buffer-70℃付近という 計算が成り立つが、それ程簡単では無いようだ。 |
|||
2.熱計算 |
|||
| 熱計算は本気でやれば意外と簡単、といいつつも、随分時間がかかってしまった。 SI単位に馴染めてないのと、参考書も結構古いので、未だに cal とかkgf/cm2を使って計算している。 計算はしたくない、とにかくベンチ取るだけに冷やしたい向きには、 冷凍機冷却法よりも、LN2とかドライアイス等、最初から冷えてるやつが お勧め。 冷やすための努力や計算、理論も殆ど不要で勝負も早い。 |
|||
| 吸熱量を設定 | |||
| CPUの発熱、ペルチェ併用の場合は更にペルチェの発熱、周囲環境からの 吸熱を推定して吸熱量を設定する。 私の例だと、intelのCPUで、eva単独で冷却する場合は50〜70W、 ペルチェ3枚並列併用で280〜300Wに設定。 |
|||
| モリエル線図(P-h Chart)を使用して計算 | |||
| 上記概算冷却温度と使用環境温度から、冷媒循環量、必要なcomp能力を算出。 こいつが読めなきゃ、話にならない。 肝心の線図は、参考書、冷凍機のカタログや取説についているが、 R22やR134a以外の特殊なものは、 日本冷凍空調学会で買うしかない。 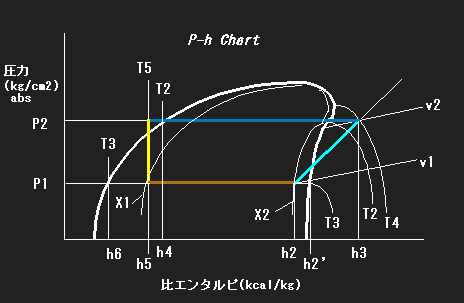 |
|||
| 冷媒循環量=吸熱量/冷凍効果 | |||
| 冷凍効果 compに吸入される冷媒(例:飽和蒸気)の比エンタルピから、 膨張弁から吐き出す冷媒(湿り蒸気)の比エンタルピを差し引いたもの。 |
|||
| 冷媒循環量×compに吸入される冷媒の比容積=compの実吐出量(排気) compの実吐出量(排気) =compカタログ上の能力(シリンダ容積と回転数)×体積効率 出力600Wのcompを使用し、ペルチェ併用での計算例 諸般の事情から、湿り圧縮の冷凍サイクル、キャピラリは夏冬切り替えで対応 何通りかの状態を想定して計算し、条件を満足しそうなものを抜き出してつなぎ合わせた。 |
|||
| 誤って理解しているかもしれないので興味のある方は参考書を読んで欲しい... | |||
準備したcompが所要の冷媒循環量を処理できない場合は、温度条件変えて 再度計算やり直す。 また、季節によって、凝縮温度が変わり、比エンタルピやキャピラリ流量も変わるので、 何通りも計算する必要があるだろう。 体積効率については、圧縮比が高くなるほど小さくなってしまうが、 データは公開されていない。 私の場合0.7と仮定して計算したが、ほぼ計算通りの冷却能力が 確認されたので、ほぼこの辺りと考えて間違いないようだ。 今回使用したcompと同形式で、ほぼ同能力のcompが搭載されている、 メーカー製冷凍機について、冷凍能力とcompの吐出量(何れもカタログ値) から、逆算して体積効率を推定すると、圧縮比12で0.82〜0.89であるから 流石と言うしかない。 低温用に特化した仕様であるので、当然といえば当然、素人が空調機を 改造したもので、ここまでの能力を引き出すのは難しい。 R134a用レシプロのメーカー製冷凍機で同様の計算をしてみると、 圧縮比8で0.5〜0.55でほぼ予想通り、やはりレシプロは良くない。 ただ、メーカーによっては、同出力で10%以上能力の大きいものもあるので、 一概に決めつけられないが... また、カタログのデータから、comp出力−吐出量の関係を求めてみると、 次のようになった。 吐出量m3/h(60Hz)=(出力W-150)×0.0038+0.65 ロータリ 吐出量m3/h(60Hz)=(出力W-75)×0.004+0.8 レシプロ 50Hzの場合は、60Hzの約83% compの出力はエアコンのカタログに掲載されているので参照されたい。 冷風機等は出力が掲載されていない。 根拠はないが、ほぼ消費電力の60〜70%程度が出力と考えれば良いのでは ないだろうか... その他、compのマーキングや刻印にも、出力と関係ある数字が、 入っていることもある。 |
|||
| キャピラリ設定 | |||
冷媒循環量、冷媒過冷温度と使用環境温度等から、参考書の図表を用いて キャピラリ長さを計算する。 凝縮温度で高圧側の圧力が随分違うから、当然、流量も変化する。 元々キャピラリは、負荷や環境条件がほぼ一定で稼働させるのに適しており、年間を通して安定稼働させるには無理がある。 例えば、冬に凝縮温度15℃で5mのキャピラリ使って調整していたとすると、 夏に凝縮温度35℃で、冬の約1.4倍の冷媒が流れてしまう。 凝縮温度が15℃から35℃になると、冷凍効果も2割方低下する。 この低下分を差し引いても、20%程度過剰に流れてしまうことになる。 よって、夏と冬では、異なる長さのキャピラリが必要になる。 以上はあくまでも計算結果、実機での調整は必要と思うが、 この算出法で得た値が、ほぼ的中するから素晴らしい。 また、キャピラリ入口に於ける液冷媒の過冷度でも、 随分影響を受けるので、戻り管にキャピラリを沿わせる、沿わせない、 といったことで流量を調整する手段も残されている。 著作権のこともあり、ここに図表を掲載するのも問題があり、 しかも、説明が難しいので省略(興味のある方は参考書で...) |
|||
| eva設計 | |||
| 実はこれが一番難しい。 evaは水枕と違って内部を流れるのは湿り蒸気、液体に比べ伝熱効率は桁違い に低い、伝熱面積と、流速で効率アップしないと使い物にならない。 参考までに、空調用のeva内径は、冷媒循環量10kg/hで1/4"銅管相当が適正。 CPU冷却用の低温evaだと、蒸気の条件が違うので、もう少し太くても 良い様な気がしないでもないが..... 10kg/hは、ペルチェ併用の時よりやや多い程度、 ペルチェ使わない時の冷媒循環量は、1〜1.5kg/hだから、 CPUをevaで直冷する場合は、内径3mmもあれば十分。 ちなみに、ペルチェ併用eva想定して、参考書片手に計算してみると、 伝熱面積200cm2・交換熱量280W・冷媒循環量6kg/hで、内径4.5mmと10mmの evaで計算で比較すると、冷媒→内径表面への熱伝達率は2倍以上違う。 これを基に平均温度差を算出すると、何と10℃近くの差が出る結果が出て しまった。 これが正しいとすれば、いくら冷媒蒸気は冷えていても、 evaは冷えない現象が発生する。 |
|||
| 計算方法) | |||
| 冷媒管内熱伝達率αR(kcal/m2h)の計算 αR=(B×(G×q)^0.5)/d B:係数、R22の場合0.029(参考書) G:冷媒流量(kg/h) d:管径(m) q:熱流束(kcal/m2h) q=Q/A Q:通過する熱量(kcal/h)・・・eva伝熱量 A:通過する面積(m2)・・・管内壁面積 |
|||
| 熱貫流率の計算 | |||
| 1/K=1/αR+1/αRS+L/λ から 熱貫流率K(kcal/m2h)を求める。 L : evaの厚さ×1/2とした(m) λ: evaの熱伝導率(kcal/mh℃) 1/αRS: 管壁の汚れ係数、銅管の場合αRS=10000(kcal/m2h℃、参考書) |
|||
| 平均温度差の計算 | |||
| Q=K×A×dtm から、平均温度差dtm(℃)を求める。 |
|||
| 計算してみると冷媒蒸気とeva間の熱抵抗が予想以上と言うことに驚くはず。 素材をいくら厳選しても、ここでの損失は桁が違う。 計算の詳細は説明が難しいので省略(興味のある方は参考書で...) |
|||
余談だが、masamoto式evaは相当クネクネしている。 通水圧損データから推定される直管相当長さは何と4.45m、実管長は1.6m程度 だから、残り約2.85m分はクネクネによる損失、直角曲がり部分の個数から 、流路抵抗計算する時の直角継手係数nは、1カ所あたり約17.3という結果に、 曲げ半径は殆ど直径という屈曲な訳だから、こんなものかも.... |
|||
ちなみに計算法は、 1. 通水試験し、単位時間あたりの流量を求める。 2. ポンプの性能曲線と流量から圧力損失を推定。 3. 管径・流量から求められる流速によりレイノルズ数を求める。 4. レイノルズ数、管壁粗さ、管内径寸法により、 ムーディの式から管摩擦係数を求める。 5. 2、4の結果からダルシー ワイルスバッハの式で管長を計算。 この水で求めた結果使って、冷媒蒸気を流した場合の圧損試算する。 冷媒がevaに吹き込まれた時は湿り蒸気、それがeva内部での移動と共に 内部で蒸発し膨張する。 つまり、体積が膨張するに従い流速が変化するので、単純に計算できない。 苦肉の策として、 evaを10分割し、モリエル線図から得られる出入りの蒸気乾き度と 、冷媒循環量から、 分割ブロック毎の圧損を計算し、その結果を合算したて計算してみた。 圧損計算値は、 真夏の条件下eva-40℃では0.18kgf/cm2、 春先の条件下eva-45℃では0.13kgf/cm2、 真冬の条件下eva-47.5℃では0.12kgf/cm2 この温度域で、この圧損は約5℃に相当、以外と大きい結果に.... |
|||
圧損計算法は、 1. モリエル線図からeva入口と出口に於ける蒸気の乾き度を得る。 2. evaを10等分したとして、1〜10の各部の蒸気の乾き度を計算。 3. 以下7.迄、各部について、 乾き度、液体と飽和蒸気の比容積から湿り蒸気の比容積を求める。 4. 湿り蒸気の比容積と冷媒循環量及び管径から流速を求める。 5. 流速、動粘度、管径からレイノルズ数を求める。 動粘度は、液及び飽和蒸気の動粘度と、液と飽和蒸気の比から計算 (実はここがちょっと怪しい? 湿り蒸気のデータが無いので...) 6. ムーディの式から管摩擦係数を求める。 7. ダルシー ワイルスバッハの式で圧力損失を計算。 8. 10等分各部の圧損を合計して、evaの圧損とした。 よって、細くてクネクネしていても大勢に影響なしとは言えないが、 流速と伝熱面積にポイントを絞ると圧損が大きくなる、圧損に拘りすぎると 冷媒の湿り蒸気が蒸発しきれない。 どのようなevaが適しているか、よく検討してから構造設計に取りかかろう。 それと忘れてはならないのが耐圧強度、水冷の時とは訳が違う。 いくらevaは低圧側と言っても、せめて20気圧位には耐えないと怖い。 しかも常温と冷却の熱サイクルが印加されるので、材料の選定や工法も 自ずと絞られてくるはず。 |
|||
| 3.構造設計 | |||
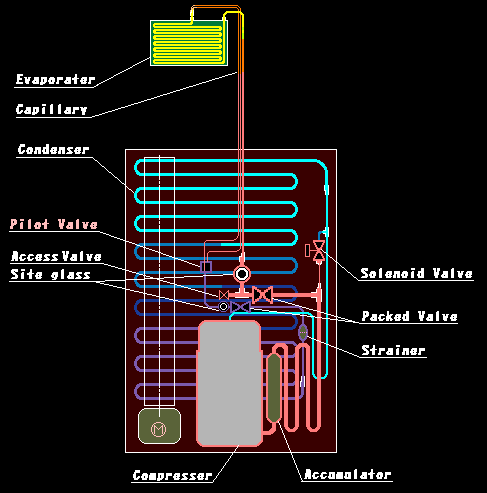 |
|||
| 機器配置 | |||
| 「地球上にあるもの全て重力の影響を受ける」が基本。 流れに無理が無いような機器配置が肝要。 配管中は冷媒だけが循環してる訳ではない、冷媒中にはcompのオイルが 溶け込んで流れている。 evaの中で冷媒が蒸気になると、オイルは蒸発しないのでeva内に残され、 冷えて粘性が上がりネバネバとなったオイルが、冷媒蒸気に吹かれながら、 やっとのことでcompまで戻ってくる。 オイルが配管中に溜まってcompに戻らなければ、体積効率低下と 極端な場合はcompの焼き付きを起こす。 |
|||
| 配管 | |||
| 継手は圧損が生じる、液管で一旦絞って拡げればガス化することもある。 また、戻り管では流速が重要、稀薄な飽和蒸気で粘ったオイルを戻すには、 冷媒循環量にもよるが1/4"管でも太いことがある。 なお、参考書によると、戻り管とキャピラリ間の熱交換は、キャピラリの 凝縮器側に近い部分と、戻り管のevaに近い部分で0.7m以上沿わせて熱交換 させるのが望ましいとのこと。 エアコン室外機の様なサービスバルブやパックレスバルブを取付けて おけば、冷媒を抜かなくても、eva交換やキャピラリ調整出来て便利。 その都度、冷媒を大気に放出しないのだから、地球にも優しい。 |
|||
| ガス量 | |||
| 機器配置や配管が決まったらガス量を計算、内部の容積と、各部の状態を 細かく分けて、温度と状態(液、湿り蒸気、飽和蒸気、過熱蒸気等)で 冷媒量を積み上げ、冷媒量を計算する。 comp内部の容積も忘れずに、それとオイルに冷媒が溶け込むことも... キャピラリ入口は液封(液が充満)が大前提、ガス欠しない量かつcompが液を吸い込まない量。 責任は持てないが、evaとキャピラリ交換で冷凍機に転用した場合、 元々の機器に入っていたガス量のほぼ60〜80%と考えれば良いと思う。 液冷媒がカスレタ状態に、冷媒量を微妙に調整し、極限まで冷やす方法もあるようだ。 個人的な意見だが、 いくら冷えたと言っても、負荷がかかると全く実用にならない。 ヒートバランスが崩れた時、キャピラリ中の冷媒発泡点が凝縮器側に移り、 キャピラリの中は液とガスの混合気が流れるといったことが起きてしまう。 また、立ち上げ時オイルが冷媒をたっぷり溶かし込んでるから、オイル温度が上昇するまでは完全な冷媒欠乏状態、冷え出すまでの時間がやたら長い。 冷える冷えないは冷媒流量で調整するのが正道。 基本的には、最適キャピラリの選択。 大技なら、電磁弁等によるキャピラリ切り替え。 小技なら、キャピラリ入口での過冷度調整や、コンデンサ冷却ファンの 回転数調整で凝縮温度を調整する。 ただし、コンデンサでの調整は、冷凍効果の点ではマイナスとなるのであまりお勧めできない。 |
|||
トップページへ/戻る/次へ