| プログラムタイプの温度コントローラー (CHINO製) |
|
かなり古い物だが、精度的には問題なし。
K型熱電対専用、元々の用途は、電気炉とか、環境試験機制御用に使われるものらしい。
  |
|
デジタル温度計 (YOKOGAWA製) |
|
こいつもかなり古い物、製造は1992年らしい。
精度は温度コントローラよりも良いようです。
測定範囲-160℃〜1372℃、確度±0.3% of rdg +0.7℃(at 0〜±199.9℃)

|
サーミスタ温度計 |
| 左: |
-50℃まで計測可能なステンレス保護管付きセンサの温度計 3,500円位、2次冷却水温の測定に使用中。
|
| 中: |
-50℃まで計測可能、ゴマ粒大サーミスタセンサを使用したもの、センサは2個、2カ所を切り替えて測定。 つい最近まで、水枕とバッファーの温度測定に使用、3,500円位。
|
| 右: |
-40℃まで計測可能、表示部の下にステンレス保護管付きセンサー、表示部を傾けるとスイッチが入る。 -25℃以下は精度は±1℃、結露防止循環温水の水温測定に使用、3,000円位
|
| |
  
|
サーミスタを使用したデータロガー |
|
2CH入力で、各チャンネル8000データを記録できる優れ物。
ESPECは恒温槽メーカーのタバイのブランド名、タバイが売るだけあって精度は、そこそこのもの(T&D社のOEM製品?)
これは、勤務先からの借り物、-60℃用のオプションセンサを含めると、一組約3万円
 |
|

|
|
収集したデーターはRS232C経由でPCへ、専用のデータ処理ソフト付き。
表示内容は、昨年末に計測した水温データ
・水温14.3℃から、2次冷起動と同時にペルチェ通電、PC起動、21分後には、水温-21.8℃で、水枕温度-18.6℃、バッファー温度-60℃
・その後更に水温は下がり、-26.6℃で水枕-22.2℃、バッファー温度は計測限界の-60℃(水温-21.8℃時の水枕温度と、この時の温度差3.6℃から推定されるバッファー温度は-63.6℃)
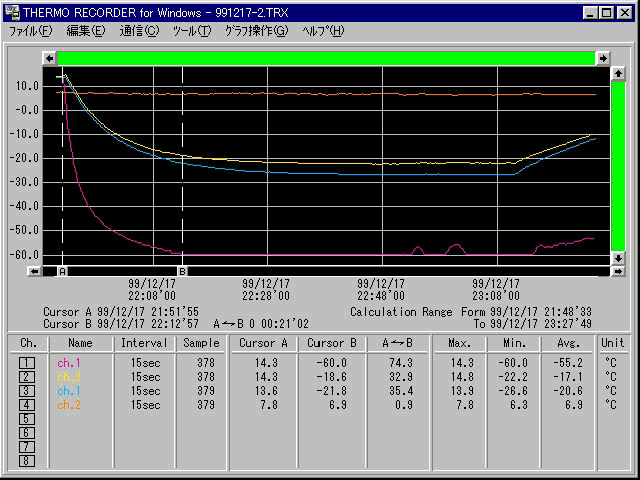 |
温度コントローラ |
|
10種類の熱電対が使用できます。1個3,000円で手に入れた中古品。
T型熱電対を接続、-50℃以下のバッファー温度測定と、水冷ヘッドに使用し、接点出力により、ペルチェ事故防止に使用の予定。
その下にあるのは、600Wスイッチング電源。
VRにより8〜16V可変の12V53A出力、ペルチェ6枚は余裕。
 |
温度コントローラ(その2) |
|
オリジナルマインドさんに安く出ていたので、?000HIT辺りの記念品に、とりあえず多めにGET!!
相当古いものではあるが、温度計としては十分使用可。
ただし、データシートや取説は無く、メーカもShinkoというだけで、中身は全く不明
K型熱電対を付けて調査し、次のことがわかった。
電源:AC100V、制御温度範囲:0〜400℃、出力:SSR DC28V、ON/OFF加熱制御(設定温度より低い場合出力)、
警報出力は不明
温度表示:氷点下も可
ただし、氷点下補完はされていないようなので、-30℃以下は高めに表示する(秋月の温度計キットを0-100℃校正したのと同じ)
JIS C 1602 熱電対の氷点以上と氷点下の補完式の差から、表示温度に対する補正温度を求めてみた。
例:表示温度が-72℃なら、実温度は(-72)+(-9)=-81℃
|
| |
 |
|
表示温度 |
補正温度 |
|
|
|
-78〜-75℃ |
-10℃ |
|
-74〜-71℃ |
-9℃ |
|
-70〜-67℃ |
-8℃ |
|
-66〜-62℃ |
-7℃ |
|
-61〜-57℃ |
-6℃ |
|
-56〜-51℃ |
-5℃ |
|
-50〜-44℃ |
-4℃ |
|
-43〜-36℃ |
-3℃ |
|
-35〜-26℃ |
-2℃ |
|
-25〜-12℃ |
-1℃ |
|
-11〜0℃ |
-0℃ |
温度精度確認 |
低温域の温度表示が妥当なものか気になっていたので、ドライアイスの温度を測ってみた。
本来なら、エタノール+ドライアイス(-72℃)でやるべきだが、横着してドライアイスに穴を穿って、熱電対を突っ込んでみた。
上から、OMRON E5CX + K -81〜-78℃
OMRON E5CX + T -81〜-78℃
SHINKO MCS + K -72〜-70℃
CHINO JP + K -80〜-77℃
ちなみに、ドライアイスの昇華温度は-78.5℃(理科年表)だから、
表面は-78.5℃としても、内部はそれよりも低いはず。
温度計YOKOGAWA 2455 + K で計測した温度は-81〜-77℃
(ドライアイスとの接触の仕方で結構ばらつく)
SHINKO MCS以外は、ほぼ妥当な温度を表示しているようだ。
SHINKO MCSもLLLとか−−−とかにはならないので、上記の補正を加えれば問題なく使える。
|
 |
|
|
|
|
熱電対 |
|
左:秋月で買ったK型熱電対
右:T型熱電対(素線)MAD LABのぐっち〜さんに頂きました。
秋葉原の坂口電熱あたりで手に入るようです。
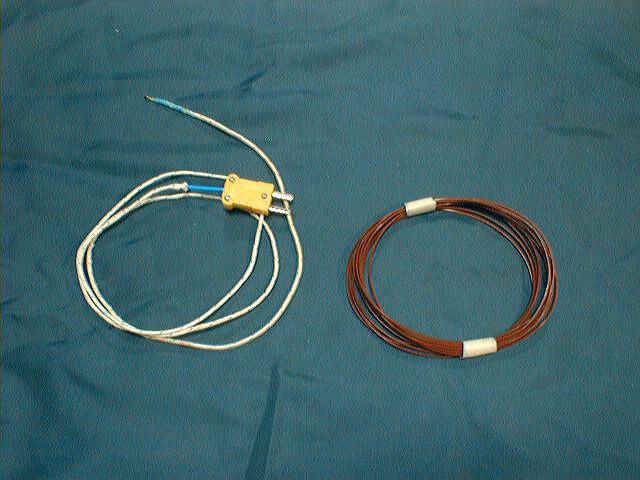 |
|
秋葉原坂口電熱で購入した、 線径0.2mmのK型熱電対(素線) 200〜250円/m 程度
右のリード線は、シリコンゴム被覆のコードヒータで外径約2.5mm、80ohm/mのもの
 |
シートカップル(K型熱電対)
asutaさんから頂いたもの。 絶縁フィルムの含めても、厚さは僅か0.2mm、素材は0.1mmの金属箔。
これだけ薄いと、レスポンスも抜群、いろいろ用途がありそう。 補償導線と組合せて使用する。 |
|
 |
熱電対の加工 |
|
素線を捩っただけでも使用できますが、 熱電対らしくするため、次の加工を行いました。
線径は0.2mmと非常に細いので、素線に傷を付けないようにテフロン被覆を 剥がします。
 |
|
被覆を剥がした素線を1〜2回捩ります。
捩った後、捩った根元をラジペンで掴み、先端からガスバーナーで加熱し、捩った部分が0.5〜1mmの玉になるよう溶融させます。
コンスタンタンよりも銅の方が早く融けますから、銅をコンスタンタンに絡めるといったイメージです。
  |
|
次に玉より先の部分をニッパー切り取り、先端を整え、玉に繋がる2本の裸線を真っ直ぐにし、長さ4〜5cm程度の細い熱収縮チューブを通します。
裸線と玉の部分にエポキシ接着剤(ボンドクイックセット)を塗ります。
 
|
|
エポキシを塗った部分に熱収縮チューブを被せ、加熱収縮させると、先端径約1.5mmのセンサの完成です。
先端の余分な被覆部は切り落とします。
  |
温度計キット
|
|
秋月温度計キットの残骸
1℃や2℃の誤差は気にならない、安価に温度測定したいという方には、お勧めです。
実はこのキット、ただの電圧計で、抵抗の倍率で微少電圧(熱電対の熱起電力は約40μV/℃)を測定しているようです。
微妙な調整が必要で、普通に校正すれば氷点下の温度はどうも高めに表示するようです。
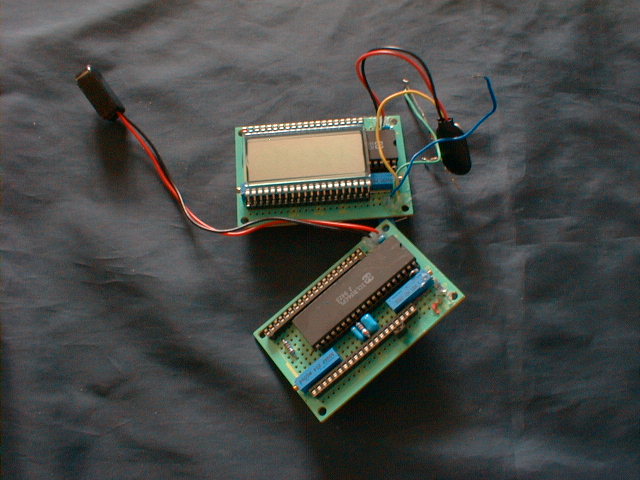 |
|
そこで、JIS C 1602 熱電対の補完式を用いてKの基準熱起電力と温度の関係をグラフにしてみると、何と0℃を境に勾配が違うこと、氷点下の直線性があまりよろしくないことが判明。
水の氷点と沸点で校正すると、温度計の表示-40℃で、実際は-42.3℃、同-50℃が-53.7℃、-60℃が-65.6℃、-70℃が-77.9℃とかなり違う事になります。
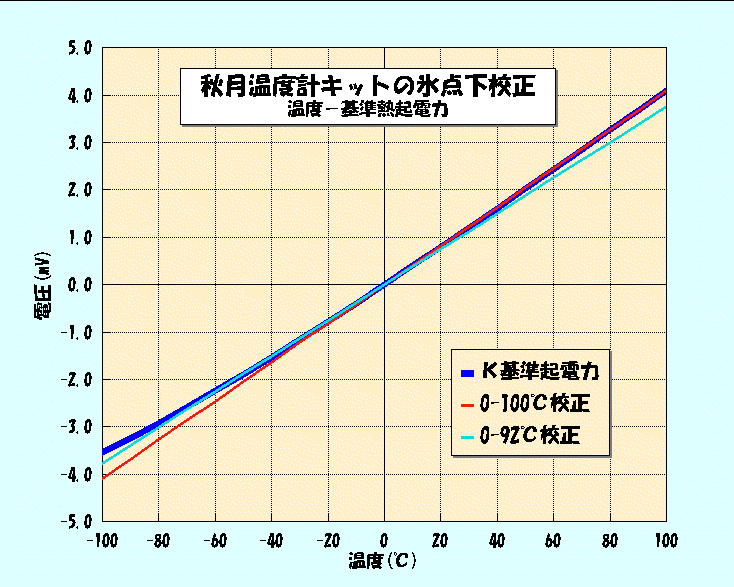 |
|
ここまでわかれば、氷点下に絞って校正することにします。、
身近な材料として、氷とドライアイス+エタノールを使用すればできるわけですが、更に簡単な方法として、氷水で0℃、水の沸点で91〜92℃と表示するように校正すれば、-70℃〜20℃の範囲で、何とか使えそうなことがわかります。
なお、この校正を行った場合の表示温度と実温度の関係は、
表示20℃で実18.9℃、10℃で9.5℃、-10℃で-9.6℃、-20℃で-19.4℃、-30℃で-29.3℃、-40℃で-39.5℃、-50℃で-49.8℃、-60℃で-60.5℃、-70℃で-71.4℃のはずです。
(実際にやってみた訳では無いので、責任は持てませんが.....) |

